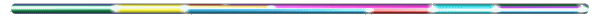
座談会 on ことば工学
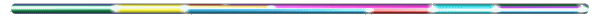
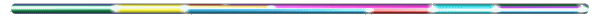
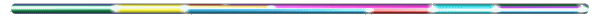

2000年お正月に人工知能学会誌の「ことば工学」特集のための座談会がひらかれた。
出席者は
松浦 寿輝氏、須永 剛司氏、堀 浩一氏、松澤 和光氏です。
前者2人が文学、芸術側からの方、後者2人と司会の阿部が「ことば工学」側からという
スタンスである。
尚、この座談会に先だって、座談会で話すと思われる内容のメモをいただいたので、
それを掲載する(以下、敬称略)。
但し、このメモよりずっと発展した話に座談会は進んだ。
ことば工学を「感性を扱うことばの学問」と見た場合、文学、美術などの目 でどのようなことを期待するか、又、疑問を持っているか? 工学からは、どの ようなことが出来ているか、では、それをどのように発展させていけばいいか などを中心に議論したいと思います。又、コミュニケーションも少し観点にい れて議論が出来ればと思っております。議論が余り工学工学したものではなく、 哲学、芸術、文学、など多岐に亙ると幸いです。
詩や小説を書いている身として、私の関心は言葉によってどのような「美」のかたち を作ることができるか、というところにあります。体験的に言えば、何かの偶発時 (出来事)の到来によってしか「美」の創造は可能とならないように思います。ソ シュールの言語学はこの「出来事」の概念をある程度共有するようですが、今世紀の 言語学の主流はむしろチョムスキー派のはずであり、その場合、生成文法の考えかた が「偶然のゆらぎ」といった出来事性をどこまで許容しうるのか、というのが私の疑 問です。最終的には、「詩はプログラムしうるのか」といったことを皆様にうかがっ てみたいと思います。%どうかよろしくお願い申し上げます。
私は、技術的に実現されたコンピュータとネットワークの、道具としての「形」につ いて考えています。
その「形」とは、それら道具のさまざまな「はたらき」が人々にどう見えるか、その 空間や対象の振る舞いです。それを考えるために「ことばの形;私たちの使っている 「ことば」が、私たちにどのようにみ見えているのか」に興味をもっています。コン ピュータとネットワークが可能にしたのものは、私たちの言語活動の拡張です。コン ピュータとネットワークを私たちの「ことばの道具」だと考えるところに、思考を組 み立て外在化し交換する道具、コミュニケーションをとおして生活と社会の活動を形 成し構築する道具の姿をイメージすることができるのではないかと思ってます。
人工知能学会は、はみ出し者の集まりであったはずだと思います。 私など、学生時代、人工知能などという怪しげな領域で研究を行っ てはならない、と先生達から言われたものです。指導教官から隠れ て、同好の士がこっそり集まって勉強会をやっていました。それが、 いつのまにか、人工知能学会もひとつのエスタブリッシュされた学 会になってしまったような気がします。
松澤さんと私が意気投合して新しいことば工学研究会というのを 作ろうということになった [1, 2] のは、 また怪しげなことをやりたいとい う思いがあったためだと思います。怪しげなことをやるには、なん といってもことばだと思います。画像でもよいのかもしれませんが、 画像は、どうしても見たもの以上の怪しさがありませんよね。その 点、ことばというのは、無限の広がりを持っているような気が致し ます。人工知能の世界でも、統語論、意味論、語用論と進んで来ま したが、その先にはすばらしく怪しげな未知の世界が広がっている 気がしてわくわくするわけです。我々理科系の人間にとって怪しげ であるというのは、測定不能、再現性なし、客観的説明理論の欠如、 などを意味します。従って、我々から見れば、松浦先生などは、怪 しい世界で輝くスターということになりましょうか。それらのスター の先生方が面白がって下さるような道具を提供してみせることが、 ことば工学の目標だと思います。どういう道具があれば面白いかは、 理科系と文科系の一流の研究者どうしのぶつかりあいからわかって くるのではないかと思います。まずは、一流の文学者や芸術家にとっ て面白いこと、かつ役にたつことが大事だと思います。その後に、 説明理論がついてくることもあるでしょう。また、その怪しげだと 思っていた世界が、現在のパーソナルコンピュータのユーザインタ フェースに代表される悪趣味の技術にとってかわって、基盤技術に なりうるかもしれない、というようなひそかな希望も抱いています。
先日の第 3 回研究会で、コンピュータに芸術は産めるか/創造性はあるか、等と 議論になりました。美や創造性は「作る側でなく見る側の判断」とは中々の達観か と思いましたが、「実は双方のコミュニケーション」との意見にも心引かれました。 「作る側」はコンピュータを介した人間とも、自発的なコンピュータ自身とも取れます。
美あるいは知識の創造/発見はコミュニケーションの上でこそ行われると考えますが、 そこに必要とされるであろう「異質性」(出来事?)は、むしろコンピュータの疑似人格(?) の方が強いかも知れません。あるいはその人格は「ことば」が「道具」に乗ったことで 発現していると見るべきなのでしょうか。ここでは「道具」も主体的な役割を果たして いるように感じられます。コミュニケーションにおけるこれらの関係について議論して みたいと考えております。
References:


|

|

|
| 松浦氏、須永氏 | 須永氏、堀氏 | 松澤氏、松浦氏 |

以下は人工知能学会誌にページ数の制約(といっても、かなり本誌でも使っているが)、テーマの関係で掲載出来なかった部分である。
● pp. 460 あたりは、元はこんな感じでした。
- 松浦
遅れまして、申しわけございません。- 堀
お忙しいところをありがとうございます。- 須永
少し始まっちゃっているので。- 堀
雑談しているうちに、いつの間にか本題に入っちゃっていまして。 「ことば工学」という何で妙なものを始めたかという話をしていまして、怪しげなことをやりたいと。 従来の自然言語処理というものがあったわけですが、それは言葉が通じるという前提のもとで、 通じる所だけを、 かっちりとやれるところだけを追っかけてきた。言葉というのはもっと広いだろう。 今ちょっと須永先生が使われたたとえ話で、従来コミュニケーションというと、 言葉の1つの塊をキャッチボールして言いたいことをやりとりしていたようだけれども、 そうではなくて複数の玉がどっと行って、そのうちの幾つかを拾って、 またこっちもどっと投げ返すというのが言葉の世界なのではないか。 そういう言葉の世界も扱えると面白いんじゃないかという話を、今していました。 それで、メールだとメールに書いたことしか伝わらないけれども、電話していると回りで聞いている人が、 あいつは何とかという約束をしていたという情報を得ていると。 本来の電話線とは違うコミュニケーションチャンネルが同時に無意識のうちにできている、と いうようなことを話していたんですが。 まさに従来の技術からだと落ちていたような世界を扱いたいというのが、 「ことば工学」の一つの動機だと思うんです。 僕の研究室でやってきた発想支援だとか思考支援も、 従来こぼれていたような情報をせっかくだからどこかに貯めておいて、 後で幽霊みたいふっと戻ってきたときに、それが何か新しい刺戟になると面白いかもしれない。 実際に、そういうことってあるわけです。 ちょっと話が飛んじゃうかもしれませんけれども、Derrida っているでしょう。 Derrida って昔から、僕はわからないと思っていた。 先生のところの若い東さんが本を書きましたね、あれが僕は読んですごく面白かったんですが。 どこまで行ってもどうせ真理というのはない、必ずこぼれ落ちる、 でもそれが幽霊でどこかにデッドストックされている届かない郵便というのがあって、 しょっちゅうその幽霊が戻ってくる。そういうふうに Derrida を説明されているんです、東先生は。 あれは、物すごく面白い。これはまさに「ことば工学」でやりたいことだな、 と僕は思ったんです。幽霊の世界を扱いたいという、言葉の幽霊の世界です。- 松澤
今いち、わからないんですが、幽霊というのは。- 堀
幽霊というのはさっきの言葉で言うと、散弾をばーっと投げかけて、だっと普通こぼれ落ちているわけです。 こぼれ落ちたものが、どこかにたまっているらしいんです。それが何かでまた立ち現れるんです。- 松澤
どこに落っこっているというか、人の間にたまっているということなんですか。- 堀
それは、Derrida だったら Derrida が書いている言葉の中なんでしょうけれども、僕もちゃんとは理解していないので。- 松澤
意識しているところは本当に部分的だから、実際にどこかにあるのかもわからないですからね。- 堀
だから東さんだと Freud と結びつけていて、無意識の世界という言い方なんです。 それもおもしろいです。Freud に結びつくというのは、ああ、そうだったのか、と。あれはオリジナルなんですかね。- 松浦
あれは、Derrida の「ラカン論」というのがありまして、真理の配達論というんですけれども。 ちょっとさかのぼると、Lacan の理論というのは有名な論文があって、 Edgar Allan Poe の短編で「盗まれた手紙」というのがあるんです。 ある手紙が盗まれて、それを大臣が、悪いやつなんですけれども隠し持っていて、 それをどこに隠しているかという謎をめぐる短編探偵小説みたいなものですけれども。 実は、だれでもが目につく状差しの中にぽんと置いておいたんだというのが落ちで、 どこか秘密の引き出しに隠しているんじゃなくて、 だれでも目につくところだから封筒を引っくり返して、手袋を裏返すようにしてぽっと置いておいたという。 それを Lacan が分析して、非常に複雑な分析なのでよくわからないですけれども、 そこからさらに Derrida が出していることなんですが。 要するに東君のポイントというのは、手紙が配達されるわけなんですけれども、 その手紙が配達される途中でかすめ取られてしまい込まれているんだけれども、 実はだれでも目につくところに置いてあったと。 だからちょっと僕も幽霊の問題とどうつながるのか忘れちゃいましたけれども。 真理を配達しようとするんだけれども、途中でかすめ取られて、 あて先に届く途中でいわば誤配されて、正しい届け先には到着しないんです。 誤配されてストックされているということなんでしょうか。 たしか、そこに結びつくんだと思うんです。- 堀
無意識世界があるんですね。 無意識世界というのはどこにあるのかわからないのですが、個人なのか、コミュニティーなのか。- 松澤
つながっているという話もありましたね。- 松浦
郵便モデルというのは、コミュニケーションのモデルとして古めかしいといえば古めかしいんですけれども。 逆にeメールの時代にプリミティブな郵便のシステムというのを持ってきて誤配の問題というのを出したところが、 東君のポイントなのじゃないかと思うんですけれども。 僕は、Lacan も Derrida も難しくてうまく説明できなくて。- 堀
東さんに来ていただいた方が。- 松澤
喩えでいくと、eメールだと本当に届いちゃうものしかなくて、こぼれるべきものが出されていないということになるんですか?- 堀
でも、実は「ことば工学」の世界でかすめ取ったなんて。- 松浦
Poe の短編の題名は``The Purloined Letter''というんですけれども、 steal (盗む)ではなくて、purloine というのはかすめる、かすめ取る、 ちょっと違うように言うらしくて、そこもすごく気取った手つきで分析しているんですけれども。- 堀
松浦先生と蓮實先生、あと小林先生が UP で対談されていましたね。 表象文化のときに。あの話もとても面白かったんですが、表象というのは我々の世界の非常に共通課題だと思うんですが、 あの対談は真理と従来の自然科学が思っていたのは非常に狭い範囲であって、 その周りに非常におもしろい世界があるというのをそのまま扱おうとしたのが、表象文化の一つの世界なのかなという印象を持ったのですが。- 松浦
そうですね。自然科学とどういうふうにドッキングできるかは、僕もよくわからないんですけれども。 ちょっと話はそれるかもしれませんけれども、コミュニケーションというのはさっきの電話のお話もそうだと思うんですけれども....
● pp. 461 の右側あたり.... 「心」について語られていた箇所
- 堀
そういうところで何かさらに変な道具を入れると、またその世界が広がると嬉しいなというのが僕らなんです。 ちょっと話が違うんですけれども、大竹しのぶの写真集、 Derrida が文章を書いているんです。 小林康夫訳なんです。小林先生が訳して。普通の意味では何を書いているんだ、これ、という。 それが、10ページ近く書いてあるんです。Derrida は大竹しのぶを知らないらしいとか。 何を書いてあるのか、普通の自然言語としてはやっぱりわからない文章ですけれども、 Derrida のじゃ。でも何となく、この写真集とこの後書きを対にすると何か別の世界になるんです。 そういう世界というのは面白いなと思って。さらにそういうところで計算機が……。 すぐに計算機と言わなければいいんですが、言う必要はなくて、 何か言葉の世界というのもまだまだ従来の自然言語処理が扱っていたのと全然違う面白さがいっぱいあると思うんです。- 松浦
僕は好奇心でお伺いしたいんですけれども、「人工知能学会」というような形で活動なさっていて、 人工知能の理論でいうと心という概念はどういうふうに扱われているんでしょうか、あるいは定義されているのでしょうか。- 堀
人工知能と心理学の境界の認知科学の領域で、心とは何かというのは僕らにとってやっぱり大問題で、 いろんな立場の人が議論というか、けんかをずっと続けている状況です。 人工知能や認知科学の連中の一つの仮説は、心というのは記号処理として説明できると。 言語、画像、すべての入力情報を含めて、心の中に何らかのリプレゼンテーションの世界があって、 リプレゼンテーションの操作体系として心がある、 というのが一つの記号論的な心の捕え方、仮説です。ここ10年来、もうちょっとでしょうか、 人工知能にしろ認知科学にしろ言い始めたのは、どうも記号処理の閉じた世界だけでは心は議論できない。 マインドボディープロブレムのボディーの方をまっとうに扱うしかない。 身体性の問題をです。心を議論するときに身体性をどう取り込んで議論するか、という方向に一つは行きました。 身体との組として心の議論をどうを捕えるか。もう一つさらに踏み込むと、 心というのは他者との相互作用等も含めて、ここに一つ心が浮かんでいるというよりは全体の相互作用プロセスのようなものを捕えたい。 身体性もコミュニケーションも他者も含めてです。そういう枠組みができるだろうかというあたりで、うろうろしているという感じじゃないかと思います。 ただ人工知能というと殆んどの人が、計算機上で何かモデルをつくって心の一部を再現することによって心のあり方を探りたいという人たちですから、 計算機の上で何か再現しようとすると記号処理としてモデル化するというのが一番主流のやり方と。 それにそれだけではなくて、身体性を伴うロボットを使ってという話が一つはあると。 もうちょっと言っておかなければいけないのは、人工知能の連中、心を計算機に持たせたいと思っている人はいることはいます。 我々は strong AI と、機械がまさに心を持ちうると主張する人たちです。 そうではなくて、ただ心が知りたいんだと。そのために計算機を道具として使ってモデル化して、分析の道具として、 あるいはシミュレーションをすることにより、心のあり方の一部を知りたいという立場もあります。 それから、全く心なんて関係なく、コミュニケーションの道具として役に立てばいいというような方向ももちろんあります。 それらは明確には区別がつかなくて、お互いに入り組んでいると。阿部さんの方は最近の若い人の理論はよく研究していると思いますけれども、どうですか。- 阿部
心を理解しようという人たちは、今いるみたいで、ただまだ先の話だという感じで、10年以上かかるかなというレベルです。 Strong AIと言われていたのは多分、10年ぐらい前だと思うんですけれども、最近その声も小さくなってしまって。 結局まだロボットを動かすレベルで終わっているという感じで、環境とのインタラクションをしようというのはせいぜいソナーとかカメラアイのレベルでしかなくて、 体温とか触角とか匂いとか、まだそこまで行けていないという。 多分そこまで行ければ、心まで近づくかなという感じではいるんですけれども。 だから間違っても、作家が書かれた文章が柔らかいとか、固いとか、生硬だとか、 そこまでは多分理解できないという感じです。 多分、文学賞の選考委員でも分かれるぐらいなので、コンピュータがきっちり出せるとは僕は思っていないんですけれども。 結局、好みが出ちゃうものはコンピュータにはまだ難しいということ。 考えようによっては好みというのを、確率過程とか Hidden Marcov 過程で書けるという話があって、 それをかもすと好みが出せるんじゃないかという考えがちょっとあるんですけれども。- 松浦
日本語の心という言葉は、すごく柔らかくて包容力のある言葉だと思うんです。 英語でも mind と対応しているのかもしれないけれども、もっと広いような気がします。 英語にも mind とか、spirit とか、soul とかありますし、 フランス語だと esprit か c\oeur とか、あるいは heart と mind だとか、 色々ななあれがあります。 心というのは一番柔らかくて、ぼんやりしていて、一番何か広くて、身体と対立しているわけでもなくて、 体も包み込むような。精神と身体というのが二元論であるような気がするんですけれども。 心というと、もっと精神の領域から体の方までにじみ出すような概念ですね。 だから心という柔らかな言葉と、コンピュータのハードウェアみたいなのが一番そこできしみ合うような2つの領域かなという気がしたので、そういう形でお聞きしたかったと思ったんですけれども。- 堀
それがきしみ合うのではないかもしれないような道具を楽しみたい。 それは、非常に hard AIというか strong AI で、人間だって神経回路網の集まりなのだから、 何らかのハードウェアだと。その上に心が乗っているのだから、計算機もある種の別のハードウェアで、 その上に心が乗ってもかまわないではないかというのが、 今もそういう人はいるかもしれませんが、昔の strong AI の一つの主張で、それはそれでもちろんあり得るんですが。 僕なんかとか松澤さんとかの道具の立場は、 一見きしみ合うところで何か柔らかい部分をつくるともっと楽しくならないかということですね。 音楽を楽しむときに、どんどん新しい楽器をつくっていくと。 ピアノをつくって音楽の世界が広がるというのと同様に、 心の世界で新しい道具としてのコンピュータシステムが出てきたときに、 一見固い道具としてのコンピュータと柔らかい広がりを持った心というのが、 実は仲よく何か役に立つのかもしれない、そういうのを目指したい気がするんです。- 阿部
多分松浦さんが考えているのは、コンピュータって[1,0]の世界なんで、 じわっとしたのが表現できないんじゃないかというのが主意ですね。 多分そういうのに対して最近は統計論を入れたり、確率で逃げようという話はあるんです。- 堀
それは割と直接的な話ですね。言葉をいろいろと扱うというのは、もう少し間接的な領域もあり得ますね。 昔、電総研の橋田(浩一)さんという AI の研究者が東京女子大かどこかで非常勤講師か何かで教えていて、 そういうマインドボディープロブレムとか AI の心の考え方を授業した後でレポートを出させたんです。 心はどこにあると思いますかというレポートを出させたら、8割ぐらいは脳にあると書くんです。2割ぐらいは心臓にあると書くんですって。 これは冗談かもしれない。1名すごく優秀なというかユニークな学生がいて、今洗濯してベランダに干してあります、って。これいいでしょ、この学生。- 松澤
私も英語で心に相当する概念があるのか、よくわからないんですけれども。- 堀
平仮名で「こころ」と書いて。- 松澤
日本人だと、何となく共通意識で持っているような気がするんですけれども。少し何か捕え方が違うのかな、という気がするんですけれども。- 松浦
心が通じる、なんていうような言い方がありますね。その場合は自分の心があって相手の心があって、 それが触れ合うとかコミュニケートするという感じでもあるのかもしれないけれども、 もっとそれ以上に何かインターサブジェクティブな領域で。 こころは、私の名前があるわけでもないし、 彼の名前があるわけでもない何かにじみ出ているものがあってというような、そういう感じじゃないかと思うんです。- 松澤
例えば脳とかいうのが、科学的にわかってきても、何となく心という概念のは普通に使いますね。- 松浦
使うし、非常にリアルなんじゃないかと思うんです。 神秘的なものではなくて。気持ちが通じるとか心が通じるというのは神秘主義の話ではなくて、 非常にリアルな体験でだれでもあることだと思いますけれども。- 松澤
英語圏の人たちが、そういう意味での「心」みたいな使い方をするのかなというのがよくわからないんですけれども。 もっと操作的なんですかね。キエマ(スキーマ(?))的という言い方は変ですけれども。- 堀
どうなんでしょう。先ほどちょっと道具をつくる方の AI の立場を言ったんですけれども、 サイエンティフィックな研究としての AI の立場から言うと、非常に幅広い世界を包含する心という言葉であっても、 説明できるところから順番に説明していきたいというのが、やっぱり AI の一つの立場だと思うんです。 授業でときどき学生に聞くんですが、多くの科学者は心というのは脳の状態だと思っていると、唯物論的に。 じゃ、脳の状態と心がほぼニアリーイコールだとすると、会議中に手を挙げて、 私はそんな意見に反対です、と言うかわりに、私の脳の状態はそんな意見には反対です、と発言してもいいはずだよねと。 これ、おかしいと思う、おかしいと思わない、と学生に聞くんですが。がちがちの唯物的な学生というのには、おかしくありません、とちゃんと言う人はもちろんいますが。 ほとんどのノーマルな学生は、何か変だなと思うんです。何か変だけれども、じゃ、どうしたらいいと思う、というのを僕はいつも学生に宿題に残すんですが。 僕ら AI の立場は、それは一見変だけれども、ちょうど道で会ったときに、 今日は暑いですねと言うかわりに、今日は空気中の分子運動が活溌ですねと言うのと同じで、 暑いという統計力学的レベルともう一つ下のレベルでちゃんとつながることを説明するのが科学の立場で、 ただ適切な表現のレベルというのは二つあって、ある分類分けにおいて別のレベルで言葉を発すればそれは変なんだというのが、多くのサイエンティフィックな AI の立場です。 そうではなくて、絶対に心は還元して説明できないんだと主張する方は、もちろん哲学寄りの方にはいらっしゃると思うし、Descartes ははっきりそうですね。 実は、生物学者なんかでもいるんです。 生物学者なんかでも、心は絶対に体に還元できない別のものだと。 じゃ、君はどっちだと言われれば、僕は還元して説明できる部分は相当多いだろうと思っている、 全部と言えるかどうかはわからないという立場です。 だいぶ話が……- 松浦
さっきの確率の導入ということをちょっとお伺いしたかったんですけれども。 確率論的な揺らぎの中で、心って働いていると思うんです。つまりその次の瞬間、何をするかわからないような。コーヒーを一口飲むかもしれないし、 何か話し出すかもしれないしみたいなところで。最終的に一瞬、一瞬、 さっきおっしゃったように行動として結果するものはあるわけなんですけれども。 その都度、その瞬間ごとの心の状態というのは、いつでも8割程度これをするだろうけれども、 ひょっとしたら思い直すかもしれないみたいな未決定状態の中で揺れていて、ということがあると思うんです。 だから、心の柔らかさというのは時間軸の問題でもあると思うんです。 阿部さんの焦点はどうなんでしょうか。 コンピュータだとランダム性をプログラムするということはできるわけですね。 だからそういう意味でリジッドな、A が来たら B になる、B が来たら C になるというような条件を与えて、 必ずこうなるというような決定論的なプログラムではなくて、もうちょっと柔らかなというか、 確率的なもので導入することができるんだろうと思うのですけれども。 人の心の動きの、いつでも未来に向かってたえず未決定なたゆたやの部分があるということと、 それからコンピュータで確率的なものを、あるいは、統計的なものを導入するといった場合に、 やっぱりちょっと違うんじゃないのかなという気がするんですけれども、どうなんでしょうか。- 阿部
大体、統計的なものを導入するというのは、過去の行動から先がわかるだろうというスタンスの もとにモデル化するということで、 要はその人があることをしたら紅茶を飲むというのが例えば1週間のうちに5日もあったら、 それでモデル化しちゃうというやり方です。 余り、こういう可能性もある、こういう可能性もある、というふうには使いたがっていないと思って。 なぜそういうことをするかというと、そういう非決定性を残しておくとマシンパワーが追いつけないというのが一つある。 それで、多分やらないんだとは思うんですけれども。 例えばその先その人に何か選択させるのだったら、こういうのもあります、 こういうのもあります、と示すことはできるんですけれども、 その幾つかのパターンを並列にばっとやっちゃうということは、多分しないと思うのです。 確率といっても最終的には[0, 1]に落ちてしまって、面白くないといえば面白くないかもしれないんですが。- 須永
ただ今の話で、人工知能の話だからそういうことになったのかもしれないけれども、コンピュータは別に生きていないわけで、 人間は生きているし、生きているということはどこかで死ぬわけで、そういうコンテクストの中でたゆたう状況を我々は選んでいるというか、それで何かを決めていくわけですね。 だから紅茶を飲むとか飲まないとか、あるかもしれないけれども。でもコンピュータは紅茶も飲まないし、 別にいつかは死ぬことを待ってあしたを生きるわけじゃないから。 だからそもそも存在理由が全然違うと思うんです、人間と機械は。- 阿部
話として、存在理由を与えるということを今考えている人もいないことはないんです。 こういう方に行ったら、彼にとっては生き延びられるとかコストが上がるとか。 コンピュータにそういうふうな意識をさせようという考えをしている人も、いるみたいです。- 須永
させたとしても、それと人間が持っている存在意識と同列に扱うことができるのかというと、 さっきの Mondriaan の話じゃないけれども、それはちょっと違う。 機械の中に与えられたもの、そこはちょっと難しいね、どうなんだろう。 僕はどちらかというと、道具派なんですけれども。 道具でいいやと思っているんだけれども、コンピュータは。生きているのは人間だし、 生きている人間の方が楽しめばいいんで、コンピュータは別に楽しむ必要もないし。 機械だからというふうに思って。そういう立場で考えると。 心の問題も、我々が本当にしっかりした心を持っていることの方が大事で、 それをわかるために機械を鏡のように研究するというのは、 そこまでは僕も非常によくわかるんだけれども。機械の中にそれを実現していこうというと、 突然何かどうしてなのかなという理由がよくわからなくなっちゃうんです。- 堀
確率モデルだって、別に確率で人間の心がゆらいでいるわけじゃないだろう、とい うのをぱっとまず思うわけです......
●会議は踊る?
- 堀
まさにその場でキャンバスがわりにやるようなのも一つの形だし、 うちの研究室で角君というのがやったのは、こうやって議論しているでしょ。 どういうテーマでどういうふうに話が流れていったというのを、ビジュアライズするんです。 そうすると場合によってはぐるぐる回っているとか。 こういって、ここら辺に空白がぽっかりあいているとかいうのがビジュアルに見えるというようなのをやって。 ATR でもっと本格的にそれをつくっているんですが。そういうのも一つ可能性です。 そういうシステムをやるのは、1つはクリエーティビティが目標にあったんですが、 もう一つはやっぱり従来議論していて、ごみかもしれないけれどもだーっと落ちるでしょう、 流れから。設計なんかをやっていても、いろんなアイデアが議論していて出ているのに落ちちゃって、 議事録から全部消えているんです。 そういうのを全部拾っておくというのは、計算機の得意なところですから。 後でまた、こんなのが以前落ちていたけれどももういっぺん放り込んだらどうなるかとか。 そういうのはいろいろと可能性はあると思うんです。 それとかうちでやっぱり実験したのは、クリエーティビティの話と完全にずれちゃうんですが、 人工衛星の設計をミーティングやって、これは後でちゃんと考えないとまずいですね、 とだれかがちゃんと言っているのに忘れているんです。そういうのはでも、 計算機上に全部放り込んでいれば残っているんです。 それで計算機が、前これは後で考えると言っていましたけれども大丈夫ですか、 とウォーニングを出すと。これは実に有効なんです。- 須永
そのプロセスをビジュアライズするというのは、 どんなふうにビジュアライズされているんですか。話が、あるまとまりを……。- 堀
キーワードがアイコンになって浮かんでいるという感じです。- 須永
それは話した順序とか意味の……。- 堀
ではなくて言葉の共起関係、一部辞書を使って類似関係で、テーマが似ているという形で 。- 須永
そういうのはいい道具でしょうね、あったら。- 堀
教授会に使うと一番ですよ。- 須永
いかにぐるぐる回っているか。- 堀
検索をしょっちゅうかけるとか、先生は先週は全く逆のことをおっしゃいましたとか、 コンピュータがウォーニングしてくる。それをやると、きっと人間関係が崩れる。
●最後の一時.....
- 松浦
添削しすぎると、文章って悪くなるんです。 初発の生々しい躍動(ヨクドウ)みたいなものがあって本当は魅力なんですけれども、 自分でここは冗長だから削ろうとか、 ここの形容詞は適切じゃないとかやっているうちにむしろ個性が消えちゃって、 すっきりはしているんだけれども何か面白くない文に近づいていくということがあります。 そういうことはありますね。- 堀
そこら辺はぜひプロの方にもじっくり教えていただくと、嬉しいですね。 村上春樹なんかは、「ノルウェーの森」の手書き原稿を全部、清書を手書きでまたし直しているんだそうです。- 須永
ワープロで書いた後。- 堀
いいえ、手書きです。最初から手書きで、ぐちゃぐちゃになっているでしょ。 それを全部清書し直したんだそうです。そのときにやっぱり相当変わっているんだそうです、 もちろん。最近は全部ワープロで書いているらしいんですが、 何か最近のって書き放題書いているという感じが、 僕はするんです、村上春樹のは。昔みたいに、もう一回書き直して削ってくれた方がいいんじゃないかなという気が。 僕は素人だからよくわからないですけれども、若干そんな気がするんですが。- 須永
道具によって違ったものが出てくるんですね。- 堀
そうですね。僕は研究メモを今まで全部手書きだったんです。去年の夏から全部ワープロに、 ちょっと試しにかえてみているんです、どう変わるか。- 松浦
研究メモって?- 堀
アイデアのメモです。どうでしょう、もう十分材料はあるんじゃないですか、 8ページでしょう。8ページに収まらないくらいありそうな気がしますけれども、 どうでしょうか。- 阿部
多分、削れば8ページぐらいになるかと.... まとめられるような話をしますか。- 堀
一つだけ僕がちょっと気になっているのは、「ことば工学研究会」がそうやって非 常におもしろい世界をやるのはいいんですが、教育上の立場がやっぱりあるんで、 余り若い学生がいきなり、面白い、面白い、って変なところばっかりをやるのは、 工学としてはまずいんです。 人工知能学会としては、僕はそういう楽しみの領域は絶対必要だと思うけれども、 若い学生がいきなりこの「ことば工学」に入ってくるのもまたどうなのかという思いがちょっとあるので。 それはこの座談会の原稿にするか、僕が解説原稿に書かせていただくか。 やっぱり、かっちりとしたところを押さえてから面白い世界に入ってきてくれないと。- 松澤
私なんかも研究所のあっちでやっていたときはやっぱり、意図的に若い人は引き込 まなかったんです、強引にはね。- 堀
もちろん若い人でも、かっちりした後だったらいいんですけれども。- 松澤
そっちの方だけに走っちゃう可能性が十分にあったわけなので。それはプロでやっ ていくときに、あとあと響いちゃう可能性もあるわけだから。- 堀
デザインもそうなんじゃないですか。やっぱり、デッサンができない人がいきなり おもしろいデザインってできないんじゃないですか。- 須永
僕らはそう思っています。そうじゃない、という先生もいますけれども。- 堀
そうではないとは?- 須永
入試にも基礎的なデッサン力を見るような試験はやめちゃって、 もっと想像力が本当にあるかどうか、 18歳〜19歳の人たちの持っている想像的能力を確かめるような試験をやるべきだと、 実際やっている学科もあるし。 それは一見ヘタウマじゃないけれども、想像力なのかでたらめなのかわからないから、 ちゃんとした表現、まず目に見えているものがきちんと表現できること、 それがまず大前提なんだと言う人もいるし、なかなか難しいですね。- 堀
いきなり携帯電話をかける編集者がいる……。- 阿部
僕としては、「ことば工学研究会」では、ベーシックな話もちゃんとしてほしいなと思っていて、 Saussure の話ができる方がいればしてほしいし。 そういうのを求めているんですけれども。 どう思われているのか、僕は知らないんですけれども。- 堀
Chomskey なんかが今さら出てきてもね。Chomskey の最近の展開とか言われても、 それはつまらない気がしますけれども。それは言語処理学会とかに行ってもらって。- 阿部
構造主義はもう古いという感じでやってほしいという……。 Signifi\'e でも signifiant でもいいんですけれども、 そういう話をしてくれる人とかが来てくれると面白いと思うんです。- 堀
もちろん Chomskey 一派でも大津先生みたいにおもしろい先生がいらっしゃるので、 それはおもしろいのかもわからないですけれども。- 阿部
あと、一応感性は使いたいと言っているので、 それを支えるような基礎的な話が来てくれると嬉しい。 文学家でも、芸術家でも、言語論家でも来てほしいという感じでやっているので。 最初、そういう人を考えて松浦さんとかを選んだんですけれども....
ことば工学入門 pp. 446 -- 455

|
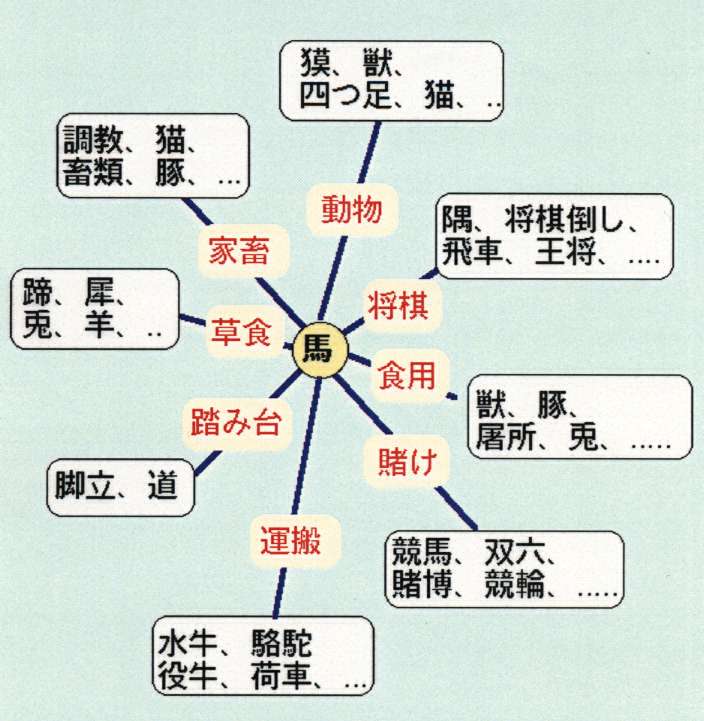
|

|

|
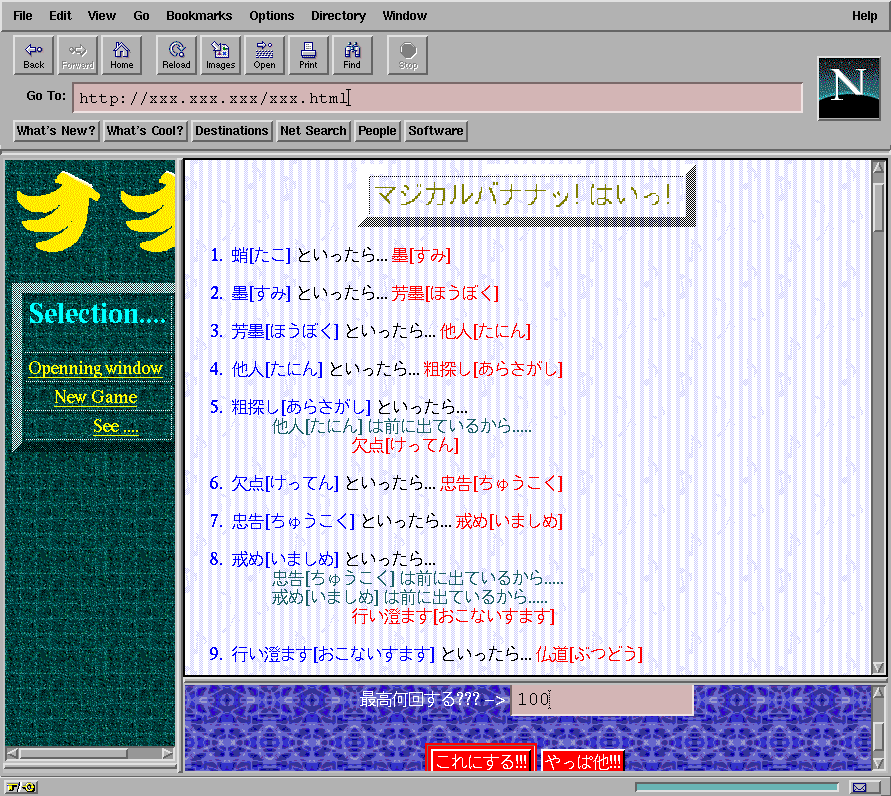
|
| 図1 | 図2 | 図3 | 図4 | 図5 |

|

|
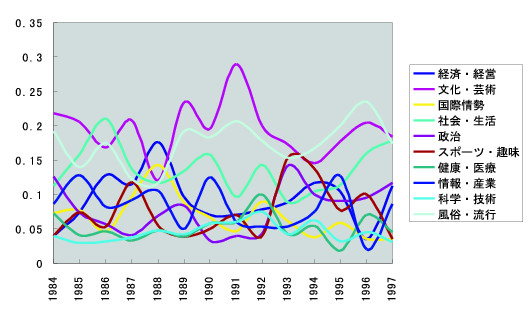
|
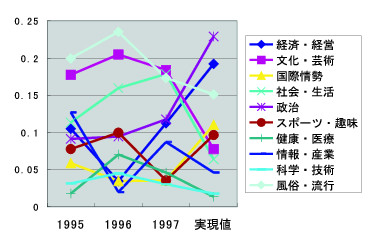
|

|
| 図6 | 図8 | 図9 | 図10 |

|
