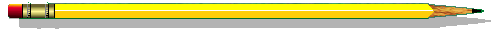
自由討論会: ことば工学とは??
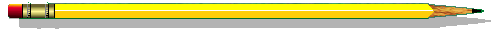
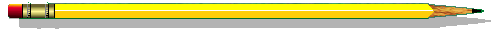
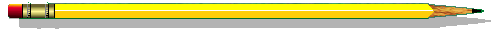
阿部より、ことば工学に関する一般的なこと(ビデオ)、 前回の予稿に書いた少し詳しい話を行なった。
つまり、ことばの性質として、を示し、更に、ことば工学の目指す所として、
- ことばの身体性
- ことばの世界-内-存在性、道具性
といったことを述べた。
- 感性/感覚を持ったことばを扱う
- 文学、芸術関係もまきこむ
以下、会場で起こった議論の概要を阿部のメモをもとに、箇条書き風に 書いていきます。あと、参考文献なども適宜追加しました。 もし、話された方の 思ったことが伝わっていない場合は、lingua@cslab.kecl.ntt.co.jp まで連絡下さい。
又、これに関する、ご意見なども、メールで送っていただけると、幸いです。このページに掲載いたします。
- 身体性を扱うには、脳のレベルの分析を行なう必要がある。
- 医学的に、広告を見た時の反応など...
- おかしな表現に接すると、独特な脳波の変化が起こる: 乾(京大)、萩原(都立大) (cf. 2/2 '99 毎日新聞 夕刊)など
- 伝わる情報とは何か?? → 身体
- 情報があるという前提
- 運ぼうとする情報がある。気づくか否か
- information flow? (cf.
- Devlin K.: Logic and Information, Cambridge Univ. Press (1991),
- Barwise J.: Constraints, channels, and the flow of information, Situation Theory and its applications, vol. 3, pp. 3--27 (1993) )
- ことばは個々の意味があって、ある規約を使って変化している
- 物価があがる
- 株価があがる
- 温度があがる
- 意味と表現
- 意味は証明の過程。言語表現は証明を惹き起こすきっかけに過ぎない。
- 手話の言語 → 工学的に可能
- 郵政省 通信総合研究所 情報通信基盤プロジェクト
- 手話認識、手話生成
- 手話による詩の朗読 (cf. Lentz E. M. VS 米内山 明宏 (木村 晴美、小林 真由美訳): Deaf Poem, 現代思想, Vol. 25, No. 5, pp. 24--27 (1997))
- 文学
- 作者の意図はわからない
- 書き手の意図とは逆の理解 → 読者が意味を作り出す
- 例えば、夏目漱石には、意図はないので、推定するのは、間違っている
- 作者の癖を見つける?
- ○○風の詩、歌を作る (cf. 阿部 明典: ことば工学の地平線 --- ``あとがき''に かえて... ---, 人工知能学会研究会資料, SIG-LSE-9901-12 (1999))
- 疑似ユーミンソング (cf. 疑似ユーミン・ソング, 単眼複眼, 朝日新聞夕刊, 1/13 (1999), 伊藤 雅光: ユーミンの言語学, 日本語学 (1997から連載中))
- デザイン
- 文字的表現、フォント etc.
- テクノロジーに依存しない
- わからずに使っている
- レトリック(形式化)、話しの順番、密度
- 日立-平凡社: 関連語が木構造で出てくる(マイペディア)
- 閉じた情報だから出来る。出来上がったものには、ブレがある
- 閉じた辞書 → ことばのブレが楽しい → きっかけ
- 意味
- 対象から変換する意味論
- → 身体へ???
- Wittgenstein の Sprach Spiel (language game)?
- 意味の認知は複雑すぎる
- プログラム言語の意味論から言語の意味論を始めると簡単? → 形式意味論
- わかりきっている所から進めるとよい → sub language
- 表面的なところのみ見る
- NY大: 限られた sub language に絞るとうまくいく
- 意味は最終的には頭の中にある
- 外在的意味でいけるものが多い
- 感性など、目標によって意味の形が変わってくる
- どういう側面が問題になってくるか??
- 個人にとっての意味は、様々であるが、コアに他の人と共有する意味があり、 それが、広がっていく。
- 社会とのかかわりが重要 → しくみを考える
- 偏在するような辞書も作ると面白い